#スパイラル(1) 経営戦略史は、ポジショニング派とケイパビリティ派の百年戦争
経営戦略の歴史は八岐大蛇(やまたのおろち)です。色んな起源をもったいろんな学派がぐねぐね常に動き回っています。複雑で難解で強力で、立ち向かう相手としては、結構最凶の部類です。でもその本質はひとつで、かつ体内に、草薙劒(くさなぎのつるぎ)を潜ませています。手に入れれば、きっとあなたの力になる武器です。この本は、あなたがそれを探しだす、助けになるでしょう。
この数十年間の経営戦略史をもっとも簡潔に語れば、「60年代に始まったポジショニング派が80年代までは圧倒的で、それ以降はケイパビリティ(組織・ヒト・プロセスなど)派が優勢」となります。極めて単純です。前者の旗手は言わずと知れたマイケル・ポーター(1947~、ハーバード・ビジネス・スクール HBS)、後者は百家争鳴ではありますが、ジェイ・バーニー(オハイオ州立大学)としましょう。
ポジショニング派は「外部環境がダイジ。儲かる市場で儲かる立場を占めれば勝てる」と断じ、ケイパビリティ派は「内部環境がダイジ。自社の強みがあるところで戦えば勝てる」と論じました。そして互いに「相手の戦略論では企業はダメになる」という研究成果を出しています。
その戦いはまるで、14~15世紀にわたる英仏百年戦争のようでした。その結着は、未だについてはいません。
#スパイラル(2) 陰にあるのは大テイラー主義(定量的分析)と
大メイヨー主義(人間的議論)の戦い
このポジショニング派とケイパビリティ派、2者の戦いは、別の側面を持っていました。それが大テイラー主義(*1)ともいわれる「定量的分析」と、大メイヨー主義と仮に名付ける「人間的議論」の戦いでもあったのです。
ポジショニング派のほとんどは「定量的分析や定型的計画プロセスで経営戦略は理解でき解決する」と信ずる大テイラー主義者でした。「アンゾフ・マトリクス」「SWOT分析」「経験曲線」「成長・シェアマトリクス(PPM)」「ビジネス・システム」「5力(ファイブフォース)分析」といったお馴染みの分析ツールを生み出しました。それで戦略をつくり、商品や生産・流通を変え、組織を変えていきました。
ところがこういったフレデリック・テイラーらを祖とする、定量的分析や定型的計画プロセスを信奉していた大企業群が、1973年のオイルショック前後の大不況に沈みます。GEを筆頭とした、大テイラー主義だったの企業群は、その見直しを進めました。分権化し、本社での分析屋や戦略担当はいなくなりました。
一方、ケイパビリティ派(の半分ほど)は「企業活動は人間的側面が重く定性的議論しか馴染まない」と考えます。人間関係論の始祖、ジョージ・メイヨー(1880~1949、HBS)からの流れでもあります。
優れたリーダーシップに点数はつけられない。組織の柔軟性を数字にはできない。学習する組織をどうグラフにするのか。その通りです。スティーブ・ジョブズを定量分析なんて、誰にもできません。
でもポーターはつぶやきます。「戦略の開発には、何らかの分析技法が望ましい」と。分析できないものを、大企業内でどう納得を得よというのでしょうか。逆説的ですが、人間関係論による経営戦略は、独裁者によってのみ可能なのかもしれません。
(*1) 『経営戦略の巨人たち』著者、ウォルター・キーチェルⅢ世による。
#ようやく出てきた大テイラー主義を超える答え。
アダプティブ主義(試行錯誤アプローチ)
スーパージェネラリスト(超 何でも屋さん)で経営戦略論のあちこちに顔を出すヘンリー・ミンツバーグ(1939~、マギル大学)は唱えます。「すべては、状況次第。外部環境がダイジなときはポジショニング派的に、内部環境がダイジなときはケイパビリティ派的にやればよい」
これはこれで正解です。どちらに凝り固まる意味などないのですから。でもこれは、彼のような秀才にしかこなせないやり方かもしれません。何でもありの異種格闘技戦(バーリ・トゥード)なので。
かつ21世紀に入って、経済・経営環境の変化、技術進化のスピードは劇的に上がり、今までのポジショニングもケイパビリティも、あっという間に陳腐化する時代になってしまいました。これでは大テイラー主義も大メイヨー主義もやってられません。
そこで出てきたのがアダプティブ(adaptive)主義です。「やってみなくちゃわからない。どんなポジショニングでどのケイパビリティで戦うべきなのか、ちゃちゃっと試行錯誤して決めよう」というやり方です。戦略の立て方も、計画プロセスもまったく変わります。これを本気でやるなら、企業組織の在り方すら変わる(オープン化)のでしょう。米軍がイラク戦争で味わった大失敗の果ての(かろうじての)成功。そこにもこのアダプティブ主義がありました。
ここまでが、超簡略版 経営戦略史です。いかがだったでしょうか。
#過去に学ぶ価値(1) オリジナルの力!
だったら今の、最先端の経営戦略論だけを学べばいいじゃないか! 過去の流れとか陳腐化した知識なんか要らないよ! という声が聞こえてきそうです。ところがそうでもないのです。ミケランジェロの彫刻は、運慶・快慶らの彫った仏像たちは、古びてしまったでしょうか。いえ、それらは今でも私たちの心を捉えます。それがオリジナル(始祖・原形)の力です。
ただ、これらの彫像と違って経営戦略論は、つくられた当時のまま伝わってはいません。ふだんわれわれが知っているのはそのごく一部だったり、それも誤解されたものだったり、なのです。過去に遡ってみると、それがよくわかります。この本では、有用と思われるコンセプトのオリジナルの意図や内容を紹介します。
「アンゾフ・マトリクス」が示したもの。BCGの「成長・シェアマトリクス(PPM)」の2軸の意味。「SWOT分析」の限界と効用。「プロダクト・ライフサイクル戦略」の神殺し。日本企業がケイパビリティ戦略に与えたインパクト。『エクセレント・カンパニー』でピーターズが訴えたかったこと、などなど。
一度、しっかり学び直してみましょう。
#過去に学ぶ価値(2) 歴史はくり返す?
「□□□□年代の終わりまでには、多くの企業は、(1)競争がグローバル化していること、(2)世界規模の競争は不可欠となっていること、を認識した」とはアンゾフの友人、ディヴィッド・ハッセイによる言葉です。さて、この□に入る数字はなんでしょう?
答えは「1970」年代、なのです。
1973年の第一次オイルショックで原油価格は1バレル3ドルから12ドルまで一気に4倍となりました。現在価値でいえば50ドル以上です。その激変に企業が経営戦略面でどう立ち向かったのか。きっとそこに普遍的学びがあるに違いません。
もちろん、歴史自体がくり返すことはありません。歴史は決してくり返さないので、むしろ「歴史に学ぶ」という姿勢は危険なものです。また多くの事柄は必然ではありません。しかし過去の事実をわれわれは必然的に起こったと見なしがちです。(このポジショニングだったから成功した、とか)。
歴史に学ぶ本当の価値は「似たような状況でもいろいろなことが起こりうるし、いろいろな戦略が有効であり得る」ということを知ることにあるのでしょう。
#学術とビジネスの橋渡し?
気鋭戦略論の過去を学ぶために、適した本がいくつかあります。その中でも「かなり網羅的な経営戦略論」の本が7冊。『戦略サファリ』、『MITスローンスクール 戦略論』、『戦略論 1957-1993』、『同 1994-1999』、『世界を変えたビジネス思想家』、『テキスト経営学 第3版』が学術系の6冊です。
ただこれらを個別に読んですぐわかるのは「バランスがいまいち」ということです。当時、経営戦略のコンセプト開発の多くを担っていたのはBCGやマッキンゼー、ベインといった経営コンサルティング会社でした。でも学術系(○○大学教授)の方が書くと、コンサルタントはほとんど登場しません。参照できる本や論文が少ないのと、「個人」があまり出てこないからです。
歴史を活き活きと描くには個人のエピソードや物語が必須です。でもこういった会社はそれを好みませんでした。あるコンセプトを、個人の業績にすることは、プロフェッショナルファームらしくないからです。でも、経営戦略史をコンサルティング会社中心に論じた『経営戦略の巨人たち』がそれを活き活きと語ってくれます。
それらを解体・再統合した本が4月27日に出版される『経営戦略全史』です。学術とコンサルティング、企業の橋渡しに、少しでもなるといいのですが。
#源流探しの挑戦。わかりやすさ・楽しさへの挑戦
調べてもわからないことも多々ありました。調べが足りないだけなのですが、何卒(なにとぞ)ご容赦いただければと思います。
ただ、昔の会社の元同僚に聞いて新たに発見したこともあれば、英語版の初版本を手に入れて確認したらわかったこともありました。特に、今の私たちにつながる、本当の源流は何なのか。そこは真剣に考えたつもりです。
なので、本編は20世紀初頭に活躍した先達たちから始めます。テイラー、メイヨー、フェイヨル(*2)です。この3人がつくり上げた「考え方」が、経営戦略論すべてのベースなのです。
もうひとつこだわったのは、わかりやすさと楽しさです。当然、わかりやすさを追求すれば、簡略化による不正確さにつながります。かつ楽しさなどは学術書にはあるまじき提供価値でしょう。
でも、そうでなければ伝わりません。なので各章には、「仮想対談」がちりばめてあります。本当にあったかもしれない会話、絶対ないけど戦わせたら面白そうな対話を9個、つくりました。テイラー対メイヨーから、アンゾフ対チャンドラー、ポーター対バーニーまで。
まずは登場する経営戦略論の巨人たちに、親近感を持ってもらえればと思います。彼・彼女らは、巨人ではあっても神ではありません。成功も失敗もする、ヒトなのです。(くり返しますがフィクションです!)
20世紀初頭の3つの源流に始まり、1950年代前後の近代マネジメントの創世、そして70~80年代のポジショニング派の君臨、80年代中盤からのケイパビリティ派の勃興、90年代後半のポジショニング派の逆襲に、2000年代のコンフィギュレーション派の登場。最後がここ10年の事業環境・戦略論についての解説と、アダプティブ戦略の実際と意味についてです。
それらを、各思想の中心人物に焦点を当てて、なぜそういう考え方になったのか、それはどんな功績を残したのか、結局どうなったのか、などを解説していきます。
なのでこの本の使い方としては、
・教科書的:経営戦略論の流れや史実、関連項目が一覧できる
・辞書的:気になる単語の意味や位置づけを索引から調べる
・百科事典的:関心ある項目について関連情報がわかる
・物語的:どうやって経営戦略論が生まれ、進化してきたかを楽しむ
があるでしょう。
すでにこういったことを学んだことのある人でも、きっと新たな視点や知見が得られます。その点については結構自信があります。なぜなら私自身が、そうだったから。
経営戦略論をめぐる50人の巨人たちの冒険活劇、そして最高の知の旅を、『経営戦略全史』でお楽しみください。
(*2)一般にはファヨールと表記されるが、Fayolのフランス語読みとしてフェイヨルとした。
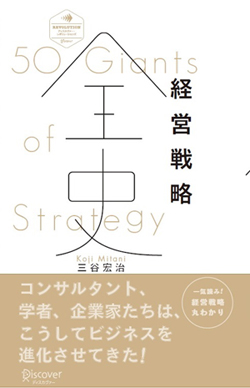 参考図書:『経営戦略全史』ディスカヴァー・トゥエンティワン、三谷宏治
参考図書:『経営戦略全史』ディスカヴァー・トゥエンティワン、三谷宏治
『経営戦略全史』は4月27日全国書店で発売予定ですが、4月18日より以下東名5店でのみ、限定部数を先行販売です。丸善 丸の内本店、三省堂書店 有楽町店、紀伊國屋書店 新宿本店3F、三省堂書店 名古屋高島屋店、ジュンク堂書店 名古屋店。



 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in