#本のアイデアはどこからくるの?
この「学びの源泉」と並行して執筆しているダイヤモンド・オンラインでは、2回連続で「本の執筆・デザインのアイデアはどこから生まれるのか」を題材にしています。5/9号では4/28刊行の『経営戦略全史』を取り上げ、5/16号では5/14刊行の『親と子の「伝える技術」』を取り上げる予定です。
「本の誕生物語」はそちらに譲るものとして、この「学びの源泉」では、前回と同じように、本の一部を抜き出して、そのコアを紹介したいと思います。
『親と子の「伝える技術」』は文字通り、親と子のコミュニケーションを扱っています。でも、おそらくは「勉強好きだが実践に苦労している」お母さん(やお父さん)向けに、3つの行動(習慣)をお奨めしています。その「脱ワンワード週間」「1分スピーチ合戦」「ダイジルールでほめる」は、いずれもゲーム性があり、親と子どもが楽しく短い時間で出来る活動になっています。
そこで主に鍛えるのは「言語」です。言葉の語彙を増やし、きちんとした文章にし、簡潔な構造を与えることで、ヒトは思考力のみならず感情表現や理解が深まり、そして、何より「幸せ」へとつながる(*1)のです!
本文にはコラムの形でわが家の3人娘が、チョイチョイ登場します。私は長女に(家業手伝いとして)頼みました。「こういう風な子育てを、された側からの意見や感想を書いて」と。
そのアウトプットがここからの5000文字です。題して「私は今、どこまででも行ける」。お楽しみください。
(*1)[第96回]幸せにつながる子育て 〜ニュージーランド1000人32年間の追跡調査から、参照
#長女:三谷家子ども歴21年。「落ち込まない」が強み
今、就活中の長女です。三谷家子ども歴も21年となりました。
もともと大学では管理栄養士の学科にいて、その専門での就職を考えていましたが、昨年末に思い立って「一般の就職活動」に挑んでいます。まったくの準備不足とも言えますが、その分、何をしても学ぶことが一杯で、毎日楽しく忙しくしています。
就職活動では、よく自己分析を求められます。自分の強み弱みというヤツです。
その中でわかった私の強みは、「あまり落ち込まない」こと。
たとえばテストを失敗しても、あんまり落ち込みません。それは落ち込んでも仕方のないことだから。たくさん勉強したのに報われなかったら、悲しむべきなのかもしれないけど、どっちみち次回のために対策を考えなくてはいけないので、落ち込んでいる場合じゃない、と考えます。失敗しても、どうすれば失敗するかがわかったと考えれば、その経験はゼロではないわけです。
そう言えば子どもの頃から、テストの後は父と反省会でした。勉強しろとは言われません。テストの点数(例えば数Ⅱ・B両方赤点とか)を見ても怒りません。でも、反省会開催は絶対です。父は私に、(1)点数を聞く、(2)平均点、偏差値を聞く、(3)何を間違えたか聞く、(4)その間違いは、勉強不足によるものなのか、ケアレスミスなのかを聞く、(5)次回のテストで点数を上げるためにどういう作戦を立てるのか聞く、(6)3日後に計画書を提出させる、を求めました。
ここまでいけば、自分の頭の中でも原因と対策がはっきりするので、次回は点数が(少し)アップします。
#日々「自分で考える」「ちゃんと文章にする」の訓練
両親は、私たちに自分で考えさせることと、ちゃんと文章にすることは徹底していました。
10歳頃「ケンカ中に妹をけった」ことで父に叱られたときも、
父「お父さんが何に怒ってるかわかる?」
私「けったこと」
父「そう、お父さんは、あなたが次女をけったことに怒ってる」
私「ごめんなさい」
父「どういう理由があっても、けるのはダメだって約束だよね?」
私「はい、もうしません」
父「どうしたら、もうしないようにできるか考えて」
私「紙に『けるの禁止!』って書いて壁に貼っておきます」
父「わかった。じゃぁそうしてください」
このやりとりで、父は私がワンワードで言ったことを文章に言い直しています。これは「ワンワードをやめなさい」という言い方ではないですが、「ちゃんと文章で話すようにしなさい」というメッセージだと感じました。さらに、叱られていると「思考停止」してただただ謝ってしまいがちですが、「対策を考えろ」と言われると、頭を働かせなくてはなりません。それも良かったと思います。実際に対策を考えなければ、また同じことが起こったでしょう。この時以来、私が妹とのケンカで手足を出したことはありません(たぶん)。
ワンワードを許さないのは母も同じです。中学の頃、子どもは結構ワンワードだったりします。
私「おかーさーん!体育着!」(玄関から叫ぶ)
母「お母さん、体育着じゃないんだけど!」
私「早くー!遅刻するー!体育着持ってきてくださーい!」
母「はいはーい♪」
遅刻ぎりぎりの私は「体育着って言えば持ってきてほしいことくらいわかるでしょ!時間見てよ!もう遅刻しそうなんだから!私が遅刻してもいいわけ?」と思っていましたが、母にとっては遅刻しないことよりも、私とちゃんとコミュニケーションする方が大切だったようです。
私も、ワンワードが良くないことはわかっていたので、母が「察しの悪い振り」をして指摘した時には、ばつが悪い思いをしたことを覚えています。そして、人に何か言うときにはなるべく文章でしゃべるようにしようと思いました。
友達や妹たちとの会話でもそうです。相手が「まじか」「やばいね」「なるほどね」とワンワードで返事をするとこちらも話を続けにくいと感じます。それで、自分はなるべく文章で答えようと思っています。
ただ、「まじか」「やばいね」「なるほど」自体が悪いわけではなく、一言で終わってしまうのがだめだと思っているので、この言葉の後に相手の意見を繰り返してもいいわけです。「まじか、○○だと思ってるんだね。」「やばいね、△△ってことでしょ?」「なるほど、□□は××なんだ。」これだけでも、ずいぶん良くなると思います。意識して変えていくことそれが無意識でできるようになっているのに気がつくと思います。
#「真剣に最後まで聴いてくれる」ことが信頼の要(かなめ)
家族とのコミュニケーションで私が一番大切だと感じるのは「絶対に真剣に聴いてくれること」です。これは、私が家族全員に対して思っていることで、この信頼感こそが家族とのコミュニケーションの要だと思っています。
私が真剣に話したいときには、考えがうまくまとまらなくても、言っていることが的外れでも、必ず真剣に聴いて受け入れてくれます。もちろん、その上で反論することはありますが、聴いてもらえることは私にとってとても大切なことなのです。真剣に話したときに真剣に聴いてもらえないと、会話をする機会が減ってしまうと思うからです。
小学生の頃、ハリー・ポッターを熱心に読んでいた私に父が「それ、おもしろいの?どんな話?」と聞きました。私は意気揚々と『ハリー・ポッターと賢者の石』について話し始めました。覚えている限りの台詞もまじえて、最初から最後まで本の内容を全部、説明しました。父はうんうんと最後まで聴いてくれました。
しかし、自分でも話が進むにつれて「自分の話が長い」、しかも「何を言っているのかよくわからない」と感じていました。結局、高校生になるくらいまで「本のあらすじ」を説明するのは苦手でしたが、どんなにへたくそでも最後まで聴いてくれるので話すのが嫌だと思ったことはありませんでした。
もし父が途中で「長いよ」と口を挟んでいたら、「長いと言われたらどうしよう」と思い、話すことが嫌になっていたのではないかと思います。
私は小さい頃から「お父さんは話をきいてくれる」という印象がありました。悪いことをして叱られているときの言い訳でも、ちゃんと言い訳し終わるまで聴いてくれるので、思ったことは言ってみるという習慣がついたのかなと思います。
#上がり症も慣れ次第!(のハズ)
考えてみれば、中学3年生頃までは相当な上がり症でした。国語の授業で本文音読を指名されただけでも、すごく嫌で、顔が真っ赤になって、ぷるぷる震えた声で読んでいたくらいです。
小さい頃から電車ではお年寄りに席を譲っていましたが、はじめの頃は父に促されて嫌々でした。もちろん、席を譲るのが嫌なのではなく、「どうぞ座ってください」と話しかけるのが恥ずかしかったのです。
でもそのうち、自分からできるようになりました。自然と席を譲れるようになった自分に気がついた時には「慣れってすごいな」と思いました。
知らない大人とのコミュニケーションって、子どもとっては大変なんです。でも、これもだいぶ慣れてしまいました。三谷家恒例お花見パーティでは、必ず途中で(かつ何度も)自己紹介タイムがあります。小さい頃は、その自己紹介が嫌で嫌で仕方がありませんでした。でも、年を追うごとに、どうせ自分は子どもなんだし、なに言っても気にされないだろうという気持ちで開き直って、克服しました。
今では、就職活動での「質疑応答の時間」に、最初に質問することだって出来ちゃいます。誰も質問しないなら私がやりますよ、という気持ちです。でも、誰か質問する人がいるなら譲ります。その替わり、「質問がなくなって場が気まずくなってきたら質問しよう」と考えて、他の人がしないような質問を考えます。
#LINEで3ヶ所5人をつなぐ
大学生になって一人暮らしを始めてから、家族とのコミュニケーションについて、より意識するようになりました。物理的に距離が離れてしまうと顔を合わせる回数が少なく、コミュニケーションが減ってしまうからです。
それを補うために私が発案し、家族でLINEをやっています。5人全員が入る「おやこ」LINE、父だけ除いた「かしまし」LINE、娘たちだけの「しまい」LINE。父と私は即レス派、母は気が向いたときにたまった会話を読んだり、自分がヒマなときには用事がないのに話しかけてきたり。次女は部活(スカッシュ)中は沈黙で、三女は受験勉強を終えて寝るまでの間だけ参戦です。
「おやこ」LINEでは毎日面白いやりとりがあり、「かしまし」LINEはわけのわからない不毛な会話とスタンプだらけ。「しまい」LINEは親に聞かれたくないヒミツの会話が満載です。埼玉、北海道、東京と、姉妹3人離ればなれですが一緒に住んでいるかのように情報共有をしています。
長女「テスト終わったぁ!やっほーい」次女「髪の毛青く染めてきたー」三女「数学教えて?」長女「寒い!眠い!」次女「札幌は今日最低気温1度!暖かいよ!」三女「ドーナツ食べたい買ってきてー」等々。
だから私は今。
このように三谷家は、とても姉妹仲がいいです。昔は、プチ喧嘩をしていましたがそのたびに父から「二人ともうるさい。喧嘩なら外でやれ!」母から「仲直りしたら入ってきてね?♪」と家から出されてしまいます。こうなるともう二人の心は1つです。「家に入りたい」で、数秒で仲直りしていました。
姉妹同士が敵対したことがないので、妹たちはいかなる状況でも味方でいてくれるという確信があります。また、家族だからこそ厳しい指摘もしてくれます。家族は私にとって、「戻れる場所」なのです。
だから私は今、「どこまででも行ける」と感じています。迷ったときにでもリスクのある方に飛び込めるし、それを楽しむ自信があります。だって私には、戻れる場所があるのですから。
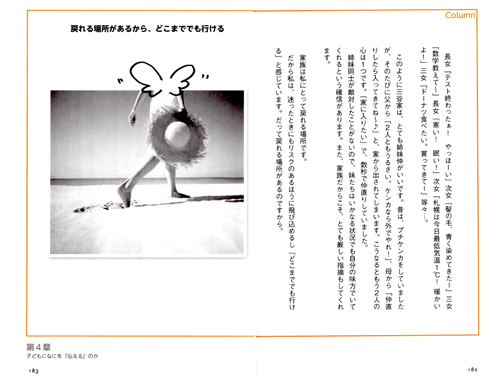
祝100回連載。次もまた1歩から
今回は、なんと記念すべき「学びの源泉 第100号」でした。アクセンチュア在職中、キャリアインキュベーションの荒井さん、藤墳さんに声を掛けていただき、足かけ8年。ここでの発信が、さまざまな出会いや執筆にもつながりました。
これからも、私の個人的な「学びの源泉」を、書き続けていきたいと思います。
また、420頁の大作『経営戦略全史』はみなさまのお陰で、ネット書店、リアル書店とも、素晴らしいスタートを切ることができました。Amazonでは総合20位、ビジネス・経済3位を達成し、その後も10位以内を安定して保っています。丸善丸の内本店といった大型書店でも、ビジネス書で5位に入ったり。
この『親と子の「伝える技術」』もクリエイターたちが、そのアイデアと労力を振り絞った作品です。多くのヒトに手に取られ、役に立ちますように。
これからも応援、よろしくお願いします。



 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in