#ディズニー映画『ベイマックス』は日本アニメの結晶体である
お正月休みの3.4日に全国で50万人を動員してトップに躍り出たのが、ディズニーアニメの『ベイマックス』(原題 Big Hero 6、12/20公開)でした。同時期公開の『妖怪ウォッチ』を押さえての堂々の首位でした。
興行収入は公開3週間ですでに40億円を突破し、ディズニーアニメでは『アナと雪の女王』に次ぐ数字を叩き出しています。
見ればすぐわかりますが、この映画は「日本」的要素が全体の7割くらいを占めます。
・主人公と兄:ヒロ・ハマダ(14)、タダシ・ハマダ(21)
・舞台:サンフランソウキョウ(街は日本語だらけ。ラーメンの屋台もある)
・ケア・ロボット:顔が神社の鈴のカタチ ( ●―● )
元となった漫画(アメリカンコミック)の「Big Hero 6」では、主人公全員が日本人で舞台は東京だったというのですから、そういう意味では当然かもしれません。でも漫画の原作者2人(*1)は、れっきとしたアメリカ人ですし、ディズニーの映画制作スタッフも、監督2人(*2)をはじめ主要な人たちは全員が外国人です。
なのに『ベイマックス』は、そのワールドプレミア(世界最初の上映(*3))が東京で行われました。製作総指揮のジョン・ラセター(*4)(John Alan Lasseter)は、言います。
「日本、東京、そして宮崎駿さんに、私は人生で大きな影響を受けてきました」
確かに、『ベイマックス』は過去の「日本アニメ」の結晶体ともいえるような作品なのです。ストーリーもそうなのですが、ここからは私が個人的に感じた、とってもディテールの話です。細部に魂は宿る。
だから、この記事を読むのは、映画を1回見たあとがいいでしょう。2回目は是非、こんなところを感じながら鑑賞いただきたい!というちょっとマニアックな鑑賞法のススメです。
(*1)スティーヴン・シーグル(Steven T. Seagle)とダンカン・ルーロー(Duncan Rouleau)。
(*2)ドン・ホール(Don Hall)とクリス・ウィリアムズ(Chris Williams)。
(*3)2014年10月23日に東京国際映画祭で上映された。アメリカでの公開は11月7日。
(*4)『トイ・ストーリー』を制作・成功させた大物で、宮崎駿とも親交が深い。2004年からディズニー及びピクサーアニメの製作総指揮を務める。
#『ベイマックス』は『となりのトトロ』であり『宇宙の騎士テッカマン』であり『人造人間キカイダー』である
主人公のヒロを守るベイマックスは、もともとが医療ケア用の柔らかいロボットです。分厚いビニールでできた風船のようなロボットで、空気を抜けばキャリーバッグサイズに収りますが、スイッチが入ればボヨンとした愛らしい感じ(*5)に膨らみます。そう、まるであのトトロのように。
主人公のサツキたちが大トトロと、最初に出会うシーンを憶えていますか?
そう、サツキとメイが小トトロを追って大楠のうろに落ちたとき、その底で眠っていたのがトトロでした。その大きく柔らかなお腹に、2人はボヨンと落ちたのでした。
『ベイマックス』にもちょうどそんなシーンがありました。
ヒロとベイマックスが高所から落下したとき、ベイマックスはヒロを抱えて自分が下になり、落下の衝撃を和らげました。落下の直前、自らの体にふだんより空気を余計に入れるという小技付きでした。
どちらも、「落下と柔らかなお腹でのキャッチ」でした。
しかし後半、鎧やロケットパンチ(これは『マジンガーZ』!)などをつけてベイマックスが「バージョン2.0」になってからは、まるで『宇宙の騎士テッカマン』(*6)でした。ヒロがベイマックスに乗って空を翔るシーンは、テッカマンが愛機ペガスに乗って宇宙を翔る姿にそっくりでした。

ヒロは激情の中でベイマックスのコア・プログラムを抜き取り、敵役を傷つけようとします。途中で、コア・プログラムを取り戻したベイマックスは、ふたたびヒロが同じことをしようとしたとき、それを拒みます。「わたしはケア・ロボットだからヒトを傷つけることはしない」と。
それはまるで、ロボットであるベイマックスに、自らの魂が宿ったかのようでした。
この「機械の心」というテーマはアトムに始まり、キカイダー(*7)受け継がれたものです。不完全な良心回路 ジェミニィを埋め込まれたキカイダーは葛藤します。しかし、「心」を持ったがゆえに自分自身で考え判断し、行動できるようになったのです。
(*5)ジョン・ラセターによれば、オムツを履いた赤ん坊と、皇帝ペンギンの子どもの形や動きを模したもの。
(*6)1975年7月から12月まで全26話がテレビ朝日系列で放送された。
(*7)1972年7月から翌年5月まで全43話がテレビ朝日系列で放送された。
#『ベイマックス』は『AKIRA』であり『科学忍者隊ガッチャマン』である
『ベイマックス』のなかでもっともインパクトが強い登場人物は、歌舞伎の隈取りの面を着けた仮面の男Yokaiでしょう。ヒロとベイマックスを襲い、ヒロが発明したマイクロボットを操るのですが、そのシーンを見た瞬間、思いました。これは『AKIRA(*8)』だと。
大量のマイクロボットをその体の一部のように操り、うごめく巨大な様は、『AKIRA』で最後、制御を失ってしまった鉄雄を思い出させるものでした。鉄雄は超能力の暴走によって、その体が膨張・巨大化してしまったのですが、Yokaiも同じく、その異形は破滅への道でした。
映画の原題でもある「Big Hero 6」からもわかるように、『ベイマックス』の後半はヒーローたちの物語です。「6」ですが、ロボットであるベイマックスを除けば人間5人のチームです。これぞまさに、『科学忍者隊ガッチャマン(*9)』や『秘密戦隊ゴレンジャー(*10)』を始祖とする、正義の味方の鉄板フォーマットといえるでしょう。
リーダーが若い熱血漢・少年タイプであること、大柄な力自慢がいること、などの類似点とともに、女性が5人中1人でなく2人なこと、その性格付けのバランスなどの相違点を楽しむのもいいでしょう。ベイマックスでは、ガッチャマンにはいない超おちゃらけキャラ(フレッド)が、いい味出しています。
(*8)週刊ヤングマガジンに1982年から1990年まで連載された。
(*9)1972年10月から74年9月まで全105話がフジテレビ系で放送された。
(*10)1975年4月から77年3月まで全84回がテレビ朝日系列で放送された。
#そして『ベイマックス』は少し未来の東京である
『ベイマックス』の舞台は、サンフランシスコと東京を足して2で割ったような未来都市、サンフランソウキョウです。製作スタッフたちが東京を訪れて取材しまくったこともあり、随所にリアルな東京が詰め込まれています。かにや巨大招き猫の立体看板や、ビルの壁面を飾るディスプレイ、街頭のごちゃごちゃした電信柱などなど。
でもやっぱりここは、未来都市なのです。本予告編の1:57のシーンを見てください。
これは、少し未来の風力発電装置です。すでにMITのスピンオフ・ベンチャーであるAltaeros Energyが、直径10メートルのプロトタイプ(*11)を製作、実験をくり返しています。


空中高くに保持することで安定した強風が期待でき、設置場所を選びません。都市におけるエネルギーの地産地消が実現できるかもしれない、未来技術のひとつです。昨年末、ソフトバンクが700万ドルの出資を決めたことで、高度100メートルでのテストも始まりました。
サンフランソウキョウには、そんな未来技術が詰まっています。あなたはいくつ、見つけられますか?
(*11)Airborne Wind Turbine (AWT) 飛行船型風力タービン、もしくはBuoyant Airborne Turbine(BAT)空中浮体式風力発電と呼ばれる。
#もうひとつの鑑賞法。どこで子どもたちが笑うのか!
『ベイマックス』は、こんなオタク的なアニメファン(だけ)でなく、子どもに大人気のコミカルな映画でもあります。映画館に行けば、上映中、子どもたちの笑い声がいっぱい聞こえてきます。では、その中でも、もっとも子どもたちの笑いをとっていたシーンはどこでしょう?
それはズバリ、ここです。まずは公式サイトにあるこちらのシーンを見てください。
ベイマックスとともに窮地を脱した主人公ヒロが、交番に駆け込んだときのシーンです。ヒロが必死で「マイクロロボットが」とか「仮面を被った怪人が」とか危機を訴えるのですが、ロートルの警官はまったく取り合いません。そのときベイマックスが、やおらセロテープで、傷ついた自らの体の修復をするのです。柔らかな腕に、穴がいくつか空いてしまったようです。
左腕に自分で空気を入れて、膨らまします。すると「ぶしゅー」っと空気が3ヶ所から吹き出します。それを1ヶ所ずつ彼はテープでふさいでいくのですが、ここで子どもたちは大笑いします。
さらに穴をふさぐにつれ、その「ぷしゅー」の音階が高くなっていくので、また大笑い。
3つふさいで修理完了かと思いきや、ベイマックスはゆっくり、今度は右腕の修理を始めます。また3ヶ所の穴から空気が吹き出して......。まったく同じ作業がもう一度、ゆっくりくり返されます。
子どもたちは、もうたまりません。面白いことのくり返しが大好きなので、ずっと大笑いです。ディズニーは、子どものことを理解しているなあと感じた瞬間でした。
私が見つけた「子ども大笑いポイント」はここでしたが、みなさんの周りではどうでしたか? そして、そのポイントは、子どもたちのどんなツボを押していたのでしょうか?
そんな鑑賞法も、2回目以降は是非してみてください。
『ベイマックス』のちょっとマニアックな鑑賞法のご紹介でした ( ●―● )。
参考資料
・「魔法の映画はこうして生まれる」NHK総合(2014/11/29放送)
・「ベイマックス公式サイト」ディズニー・ムービー
読者のみなさんへ
新年あけましておめでとうございます。2014年9月発売の『ビジネスモデル全史』、発売後即重版で4万部!そして、なんと『経営戦略全史』に引き続いて、ダイヤモンドHBRベスト経営書の第1位になりました。12月10日からは全国の主要書店さんでそのフェアが行われています。ぜひ、お手にとってみてください。
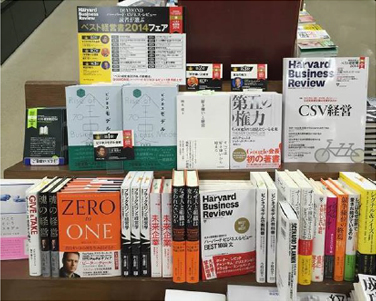
ご意見ご要望はぜひ、HPのお問い合わせまで、お寄せください。



 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in