「デザイン」という"日本語"のイメージをまず壊したい
「だれもがデザイナーになれるんです」
それが2019年リリースの著書『HELLO, DESIGN 日本人とデザイン』(幻冬舎刊)で、石川氏が発信しているメッセージの原点。クリエイティブな発想や物事との取り組み方に古くから価値を見いだしてきた欧米社会と異なり、日本では「デザイン」という言葉を用いると、モノや空間をキレイに創ることだけを指すかのように捉えられてきた。しかし「そんな狭い意味じゃないんです」というのが石川氏。「人の潜在的な課題や願望を解決すること」が「デザインする」ということ。だから誰にだってできるし、どんな場面にだって生きてくるのだという。
ここへきて「デザイン・シンキング」「デザイン思考」が最新流行のビジネス・アプローチであるかのように取り上げられるようになったが、石川氏は1990年代からこの発想を学び、実践してきた。あらゆる事象を「デザインする」視点で捉え、価値を創造してきた石川氏にとってみれば、ようやく日本語の「デザイン」が正しい意味で浸透しつつある、ということなのだろう。
ではこの石川氏は、どんな原体験から今に至っているのだろうか?
「僕はもともと料理家か建築家になりたかったんです。成果物としての"もの"を提供して、その都度"お代"を頂戴して生きていくという、とてもシンプルな図式に惹かれていました」
創造性の話として料理や建築を語る、というよりも、生き方の話として職業を考えていたあたり、現在の石川氏にも通ずる匂いがする。その後のキャリア形成の舞台ともなるロンドンに渡った経緯にも親近感が宿る。
「料理人になりたかった」青年が遭遇した欧州流学問の衝撃と魅力
「当初は日本の大学に通っていたんですが、なんとなくピンと来ない。『あれ、こんなこと学びたかったんだっけ』というような感覚のまま、語学留学という格好でイギリスに行ったんですよ」
思いのほか、ロンドンの空気は肌に合った。もともと型にはまらない発想の持ち主だったせいか、現地で大学を受験し入学することにしてしまったのだという。ファウンデーションコースと呼ばれる留学生向け準備課程で出された「何をデザインしたいのか、自分で自由に決めて、そのアイデアを提出しなさい」という課題が、石川氏の価値観にもフィットした。
「その後、向こうの大学に通い始めてからも何度も味わったんですが、イギリスでは『まず自分で問いを立てる』ところから学問がスタートするんです。『出された問いに答える』のが学問であるかのように教えられる日本とは、教育そのものの概念が根底から違っていました」
例えば、いわゆる日本の美大などであれば、アウトプットの作品をいかに美しく整え、魅力的に仕上げるか、に重きが置かれることが多かった。デザイナーを志すような学生であれば、それこそがデザインなのだと受け止めてしまいかねないが、イギリスの教育現場で何より重視されるのは、「アウトプットの目的は、そもそもなんなのか」「だれのための、どんな問いを解決しようとしているのか」「どうそれが従前のものから進化しているのか?」。それこそがデザインの本質であることを、学生は学び取ることになる。
石川氏によれば、デザインやアートに限らず、あらゆる学問に対する姿勢に以上のような視点が貫かれているのだという。それゆえ、先のお題に対する学生たちの反応も様々。紙にプリントした企画書的なものを提出する者もいれば、立体の造形物を用意して提出する者もいた。「何を提出するか」に正解があるのではない。当人がどんな問いを立て、そこにどういうアイデアやソリューションを用意するのかが求められているのだから、形はなんでも良いわけだ。その自由度や多様性、決まり切っていない解を自力で絞り出していくアクションに魅せられた。
そうして入学したのがロンドン芸術大学、University of the Arts London (UAL)。ファッション界の巨人ジョン・ガリアーノやステラ・マッカートニー、アーティストのフセイン・チャラヤン、コンランショップの創設者であるのテレンス・コンラン、そして、IDEOのファウンダーの一人である、ビル・モグリッジなどなど、そうそうたる著名デザイナーを輩出している名門だった。
「面白かったですよ、学ぶことが。1990年代当時から向こうには、アカデミックなものとアートとを融合させながらデザインを考えていくような発想が脈々と流れていて、本当に刺激的でした」
石川氏が「ビジネスだけでなく教育のあり方もデザインして、日本の現状を変えていきたい」という意向を今日示しているのも、日本におけるデザイナーやデザイナー志望者をめぐる環境に満足できないでいるから。自身がロンドンで体感したような学びの場があれば、日本や日本のデザイナーを変えていくことができると信じているからだ。
歩んできたのは「成功者のキャリアパス」ではなく「人生をデザインするための学び」
その後の石川氏の経歴は実に多彩なのだが、いわゆる「成功のためのキャリアビジョン」のようなものがあったわけではなく、魅力的な発想や姿勢、それを体現している人物との出会いをきっかけにしながら「学んでは学ぶ」を繰り返しただけ、とふり返る。パナソニックのデザインカンパニーであるパナソニックデザインへの参画も、偉大な先人たちとの出会いの連鎖からだった。
「ロンドンで活躍されていた安積伸さん(プロダクトデザイナー。世界中で大ヒットし、美術館にまで所蔵されているLEM stoolの作者として名高い)との出会いでAZUMI a studioに入ったのですが、同じ頃、照明関連のイベントで、当時パナソニックデザインにいらした西堀晋さん(プロダクトデザイナー。後にアップルへ引き抜かれiPodやiPhoneのデザインに携わっていたことでも知られる)にもお会いしていて、『一度は日本企業を経験した方がいい』という助言をいただいたんです。当時は若さゆえにピンとこないところもありましたが、人生だってデザインすべきなんだ、という考え方に触発されました。当時は日本の製品が世界を席巻していた時代でもありましたから、そこで学びたいとも思って参画したんです」
石川氏によれば「僕の学びの第1フェーズ」だったというこの時代に、製図のスキルを叩き込まれたばかりでなく、大規模組織での働き方の一長一短もまた学習したという。
「僕がイギリスの大学や安積さんのところで学んだものと違い、大企業の中では、デザインというものがまだ生産プロセスの一過程として機能していました。日本のモノ作り産業の繁栄がイノベーションよりもカイゼンというアプローチで成立していることを、肌身で感じましたし、それはそれでとても大きな学びがありました」
身につくスキルの量や密度は高かったものの、同じ作業の繰り返しという日々に疑問を感じた石川氏は「学びの第2フェーズ」をPDD innovationsで迎えることになる。デザインコンサルティングと呼ばれるものの草分け的存在の英国企業である。
「エキスペリエンスをデザインする」「イノベーションを誘発する」
「結局、僕は料理人になりたかった人間。人を喜ばせようと必死で考えて、それをデザインしてアウトプットし、渡していくような働き方が性に合っていたということです。喜んでもらえるなら料理じゃなくても、建築でもなんでもいい。結局デザイナーの仕事って、好きになった女の子を口説く時の男の子のようなものですよ(笑)。何を作って贈り物にするのかが重要なのではなくて、どうすれば彼女に気に入ってもらえるか、をいろいろな角度から検討していくことが問われるわけじゃないですか。あの手この手を考え抜いていった経験はどなたにもあると思うんですが、それこそが『デザインする』ということ。言ってみれば体験のデザイン、ユーザー(彼女)のエクスペリエンス(喜び)をイメージし、デザインしていくプロセスですよね。つまり、誰だってデザイナーなのだということです」
そう語る石川氏。PDDは、家電や自動車といったプロダクトも手がけていたが、医療やパッケージ、多様なサービス・エクスペリエンスまでデザインする幅広い分野のプロジェクトを展開していた。それが先の石川氏の思いとつながったのだ。5年間の在籍中、主に医療分野のデザインを手がけたというが、いきなりモノ作りに入るのではなく、プロジェクトそのものをデザインするところから入り込んでいける体験が糧になったという。ただし、ここでも「問いを立てる」ことの張本人はクライアントである。その問いに広義のデザインで答えを出す行程にやりがいを感じつつも、「問い」の部分から手がけたいという願望が膨らみ始める。そんなタイミングで声をかけてくれたのがIDEO Tokyo創業者のサンジン・リャン氏だったという。
「サンジンさんに会ったのは、2011年の暮れ頃でした。すでにその頃にはパナソニックやソニーの黄金期は過ぎ去っていて、『日本はかつて世界一の経済大国にまでなっていたのに、今やそうではなくなっている。それがすごく悔しいから一緒に日本を良くしていこうよ』と言われたんです。正直なところ、最初は『アメリカ人が急にそんなこと言い出しても、本当に本気でそう思っているのかな』みたいな疑念はありました(笑)。でも、彼の奥さんは日本人だし、話せば話すほど本気であることは伝わってきたし、なにより『既存のものをカイゼンしていても限界がある。日本を良くするのならば、積み上げ式ではないイノベーションを起こすしかない』という風に僕自身が強く感じ始めていたタイミングでもあったので、IDEO Tokyoの立ち上げに参画することを決めたんです」
石川氏の心に最も響いたのは、デビッド・ケリー氏(IDEOの創設者、スタンフォード大学教授)やIDEOの活動が示す、「あきれるほどの楽観性」や「圧倒的な主観性」だったという。
「イノベーションというのは、前例のない何かを立ち上げる行為ですよね。『今の世の中にこれって足りてないよね』とか『こういうのがあった方が楽しくない?』とか、そういうごく主観的なアイデアを信じ切って、とにかく楽観的に手がけていくしかありません。失敗しても挫けずに、ある種の偶発性をウエルカムするようなマインドもあって、初めて実現するのがイノベーション。どんなに美しいデザインを描いても、その生産コストを5円10円単位で切り詰めてカイゼンを繰り返すという日本のやり方に限界が来ていましたから、IDEOの思想と姿勢を東京に落とし込んでいく仕事に、真剣に取り組むことにしたんです」
(後編に続く)※2019年 6月17日に公開しました
プロフィール

石川 俊祐 氏
kesiki inc
Partner, Design Innovation
1977年生まれ。英Central Saint Martinsを卒業。Panasonicデザイン社、英PDDなどを経て、IDEO Tokyoの立ち上げに参画。Design Directorとしてイノベーション事業を多数手がける。BCG Digital VenturesにてHead
of Designを務めたのち、2019年、KESIKI設立。多摩美術大学TCL特任准教授、CCC新規事業創出アドバイザー、D&ADやGOOD DESIGN AWARDの審査委員なども務める。Forbes Japan「世界を変えるデザイナー39」選出。著書に『HELLO,DESIGN 日本人とデザイン』
デジタルコンサルファームインタビューの最新記事
- PwCコンサルティング合同会社 Technology Laboratory | 所長・上席執行役員 パートナー 三治 信一朗 氏 / 執行役員 パートナー 岩花 修平 氏(2024.3)
- NTTコミュニケーションズ 「KOEL」 | デザイン部門「KOEL」クリエイティブ・アドバイザー 石川 俊祐 氏/デザイン部門「KOEL」UXデザイナー 金 智之 氏/デザイン部門「KOEL」 Head of Experience Design 田中 友美子 氏(2021.4)
- kesiki inc 後編 | Partner, Design Innovation 石川 俊祐 氏(2019.6)
- kesiki inc 前編 | Partner, Design Innovation 石川 俊祐 氏(2019.6)
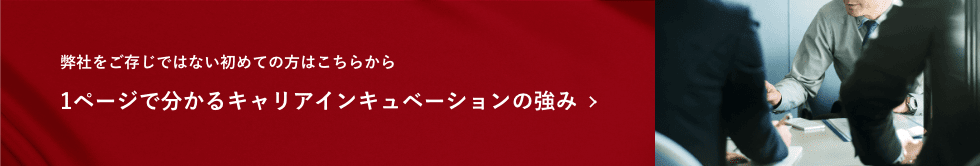




 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in