はじめに
ボーナスは、会社員にとって重要な収入源の1つであり、モチベーションを高めるための効果的な手段です。ところで、一般会社とコンサルティング会社では、その支給方法や金額にくつかの違いが見られます。
本稿では、まず一般会社とコンサルティング会社におけるボーナスの違いを比較し、次に報酬におけるボーナスの位置づけの比較、最後にボーナスの金額を決める変動要素について詳述します。
一般会社のボーナス

一般会社では(読者の方はよくご存じだと思いますが)ボーナスは通常、年に2回支給されることが多く、夏季と冬季に分かれています。支給額は基本給の一定割合で決定されることが一般的であり、会社の業績や個人の評価による影響は比較的少ないです。このため、固定型のボーナスと呼ばれることが多く、安定した収入源としての役割を果たしています。
例えば、日本の多くの企業では、夏季ボーナスは6月から7月にかけて、冬季ボーナスは12月から1月にかけて支給されます。支給額は通常、基本給の2〜3ヶ月分ですが、企業の業績や景気の影響を受けて増減することもあります。社員のモチベーション向上や生活の安定に寄与するため、固定型ボーナスは非常に重要な収入源となっています。また、住宅ローンや投資信託等においては、ボーナス時の増額もオプションとして組み込まれており、会社員の多くの方が、ボーナスを所与のものに近い形でとらえられているのではないでしょうか。
コンサルティング会社のボーナス
一方、コンサルティング会社では、ボーナスの支給方法は非常に多様です。多くの場合、年次の業績評価やプロジェクトへの貢献度に基づいて支給額が決定され、個々のパフォーマンスが大きく反映されます。これは変動型のボーナスと呼ばれ、支給額が大きく変動する可能性があります。そのため、コンサルタントは高い成果を求められる一方で、高額なボーナスを手にするチャンスもあります。
例えば、ある大手コンサルティングファームでは、年次の業績評価に基づいてボーナスが決定され、プロジェクトごとの成果やクライアントの満足度が考慮されます。優れた成果を上げたコンサルタントは、基本給の数倍に相当する高額なボーナスを受け取ることが可能です。しかし、業績が振るわなかった場合は、ボーナスが大幅に減額されるリスクもあります。
報酬におけるボーナスの位置づけの比較
また、報酬におけるボーナスの位置づけも重要です。特にコンサルタントへの転職を検討されている人は、提示された「標準報酬」(呼び名は各社によって異なりますが、いわゆる年俸に該当するもの)において、ボーナスがどのような位置づけにあるかを確認してください。
大きく分けて「標準報酬」にボーナスが含まれている会社と、含まれずボーナスは別にしている会社があります。
ボーナスが含まれている会社の場合、注意が必要なのは「標準報酬」はどちらかというと参考金額に近く、ボーナスの多寡によって実際の年俸は変動するということです。毎月の給与は、標準報酬からボーナスの参考価格を引いたものを12か月で割ったものが支給されます。一方「標準報酬」が含まれない場合、その標準報酬を12か月で割ったものが毎月の給与として支給され、ボーナスはそれらに加えて業績に応じて支払われます。
従い、給与面で複数のコンサルティング会社を比較する場合は、それらを加味したうえでの総額比較を行い、それがご自身の希望や支出計画に合うかどうかを検討してください。
ボーナスの金額を決める変動要素
ボーナスの金額を決める際には、さまざまな要素が考慮されます。筆者は複数の、それぞれ異なるタイプ(IT、総合、戦略)のファームを経験してきましたが、ボーナスを計算する要素は概ね共通したものがありました。以下その共通点を列挙してみます。
● 全社/グループ全体の業績
まず、当然ながらボーナスを支払うためには会社全体の業績が重要です。業績の多寡がボーナスの原資となります。外資系であればここでグローバルの業績も影響する場合があります。例えばいくら日本の業績が良くても、グローバル全体で不景気であれば必ずしもボーナスの原資が十分に配分されないこともありますし、その逆もあり得ます。
● 部門の業績
次に加味されるのが部門の業績です。部門をどの単位でとらえるかは各社によって異なります。大手ではいわゆるプラクティスで評価を分ける会社もありますが、ブティックファームのような小規模な会社では部門別の業績は考慮しない場合もあります。
● 個人の業績
個人の業績におけるKPIは、コンサルタントの役職によって分かれることが多いでしょう。ジュニア層においては、Utilization(稼働率)がベースとなる評価基準であり、それに各プロジェクトでの評価を加味することが一般的です。マネジャー以上からUtilizationに加え、Sales評価を見られるようになり、ランクが上がるにつれUtilizationからSalesへ評価の重みがシフトしていきます。
定量評価以外にも、マーケティング活用や人材育成など、会社基盤の構築や改善に対し評価基準を設けたり、逆に日々の申請手続き等の遅れによる減額を設定するなど、独自のパラメーターが設定されている会社もあります。
基本的には最もボーナスへの影響が大きいのは個人の業績ですが、全社や部門など、個人では動かしがたい要素も含まれているため、完全歩合制のような企業ほど、個人業績が直接反映されるわけではありません。それでも一般会社よりはボーナスの変動性が高いことを認識しておく必要があります。
終わりに
本稿では、一般会社とコンサルティング会社におけるボーナスの違い、報酬におけるボーナスの位置づけの比較、そしてボーナスの金額を決める変動要素について詳述しました。ボーナスは社員のモチベーションを高める重要な手段であり、その支給方法や金額は、企業の文化や方針によって大きく異なります。今後も、効果的なボーナス制度の設計と運用が求められるでしょう。
特に、変動型ボーナスと固定型ボーナスのバランスを取ることが重要です。社員の安定した生活をサポートすると同時に、業績向上や自己成長を促進するためのインセンティブを提供することが求められます。企業は、社員の声を聞き、柔軟なボーナス制度を導入することで、より良い職場環境を築くことができるでしょう。
最後に、ボーナス制度は企業の競争力を高める重要な要素でもあります。優れたボーナス制度を持つ企業は、優秀な人材を引きつけ、保持することができるため、長期的な成長と発展を支える基盤となります。今後も、企業はボーナス制度の改善に努め、社員と共に成長していくことが期待されます。

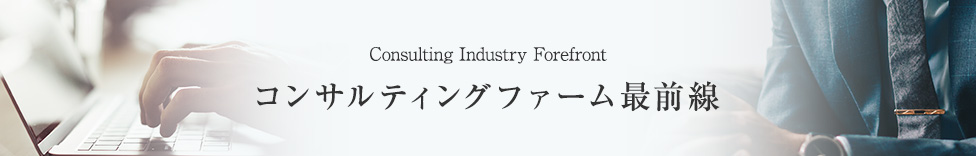



 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in