はじめに

プロジェクトを成功に導くためには、計画段階での適切な準備が欠かせません。適切な計画さえ立てられればプロジェクトの成功は半分程度保証されるといっても過言ではありませんし、逆もまた然りです。
とはいえ、多くの場合プロジェクト計画時にすべてを見通すことは困難です。何故なら、コンサルティングプロジェクトはその遂行において不確定要素を多分に含むからです。特に戦略コンサルティング案件において、クライアントとの議論の中でプロジェクトの方向性が大きく変わるようなケースを筆者はこれまで何度も経験してきました。
そうした不確実性がある中でも、プロジェクト計画を適切に策定することでその振れ幅を減らすことは可能です。今回は、プロジェクト管理の標準として広く認識されているPMBOK (Project Management Body of Knowledge) を参照しながら、コンサルティングにおけるプロジェクト計画の重要なポイントについて解説いたします。
プロジェクト計画の目的
プロジェクト計画の主な目的は、プロジェクトの成功を確実にするための指針を提供することです。具体的には、以下の目的を達成するために計画を行います。
● プロジェクトの範囲、目標、成果物を明確にする
● 必要なリソースとスケジュールを特定する
● リスク管理の戦略を策定する
● 関係者の期待とコミュニケーション計画を設定する
プロジェクト計画の主要な要素
PMBOKでは、プロジェクト計画には以下の主要な要素が含まれるとされています。PMBOKの言葉を借りると、プロジェクト統合マネジメントの管理対象である9つの「知識エリア」に該当するものです。これらは独立した要素ではなく、夫々のバランスを考慮するものです。例えばスコープを拡大するためにはスケジュールを調整しなければなりませんし、コストを増やしたりするなどが必要です。従い、全体のバランスを見ながらプロジェクト計画策定時にこれらを設計していきます。
1.プロジェクトスコープ管理計画
● プロジェクトスコープ管理計画では、プロジェクトの成果物と必要な作業を明確に定義します。これには、プロジェクトの境界を設定し、スコープの変更管理手順を規定するスコープステートメントが含まれます。
2.プロジェクトスケジュール管理計画
● プロジェクトスコープ管理計画では、プロジェクトの成果物と必要な作業を明確に定義します。これには、プロジェクトの境界を設定し、スコープの変更管理手順を規定するスコープステートメントが含まれます。
3.プロジェクトコスト管理計画
● プロジェクトコスト管理計画では、予算を設定し、コスト見積もり、予算編成、コストコントロールの方法を明確にします。これには、コストベースラインの設定や、コストパフォーマンスの測定方法も含まれます。
4.プロジェクト品質管理計画
● プロジェクト品質管理計画では、プロジェクトの成果物やプロセスの品質基準を設定し、品質保証および品質コントロールの手順を明確にします。
5.プロジェクトリスク管理計画
● プロジェクトリスク管理計画では、プロジェクトに影響を与える可能性のあるリスクを特定し、リスクの評価、対応計画、監視方法を規定します。
6.プロジェクトコミュニケーション管理計画
● プロジェクトコミュニケーション管理計画では、関係者とのコミュニケーションの方法、頻度、手段を明確にし、情報の流れを管理します。
7.プロジェクト調達管理計画
● プロジェクト調達管理計画では、外部からのリソースやサービスの調達方法を設定し、契約管理の手順を明確にします。
8.プロジェクト人的資源管理計画
● プロジェクト人的資源管理計画では、プロジェクトチームの構成、役割と責任、チームビルディングの方法を定義します。
9.ステークホルダー管理計画
● ステークホルダー管理計画では、ステークホルダーを特定したうえで、プロジェクトとの良好な関係構築やコミュニケーションプランを定義します。
コンサルティングのプロジェクト計画における重要なポイント
さて、上記を並べて眺めてみてもピンとこない方は多かったかもしれません。PMBOKはあくまでプロジェクトマネジメントのためのフレームワークであり、教科書的なものですので、この文章を読むだけで理解するのは難しいでしょう。もちろんこれら要素がプロジェクト計画におけるキーパーツであることは間違いないですが、実際のプロジェクトにおいては、解くべき課題や状況に応じて、臨機応変にこれら要素を解釈し、具体化していくことが求められます。
ここからは、上記を踏まえながら、実際のコンサルティングプロジェクトを計画するにあたり、特にコンサルタントが重視すべきものとして、4つのポイントについて解説していきます。
① スコープの設定
最もベーシックでありながら、最も重要なのがこのスコープの設定です。プロジェクトには必ず始まりと終わりがありますが、スコープはまさにこの終わりを定義するのと同義です。何を解けばクライアントの課題が解決するのか、そのために実施すべき内容(タスクや成果物)をスコープとして設定し、クライアントと合意しなければなりません。スコープはプロジェクトに何が含まれていて何が含まれていないのか、またプロジェクトのゴールを達成するために実施しなければならない作業は何か、といったプロジェクト全体の羅針盤となります。Scope of Work(作業範囲)やStatement of Work(作業範囲記述書)として整理されることもあります。いわばプロジェクトの契約における前提です。
もしあなたがメンバーだったとしたら、スコープが定まっていないプロジェクトに参加するのはリスクしかありませんし、プロジェクトマネジャーであればスコープを明確に定めていないプロジェクトを開始してはいけません。
② スケジュールの設定
スコープによってプロジェクト全体を規定したのちに、その実現をタイムラインに合わせて並べていくのがスケジュールです。スケジュールの設定において重要なのは、作業計画とアウトプットの関係性を明確にすることです。
工数(含、実行者のアサイン)とタスクだけで構成されたガントチャートをよく見るのですが、それだけでは必ずしも十分とは言えないと筆者は考えています。ポイントとしては、タスクを洗い出すだけでなく、そのタスクによってどんな成果(物)ができるのかが、スケジュールの設定において定義されているかどうかです。タスクはあくまで作業でしかありません。それによってどんな成果が期待されるのかがセットでないと、本当にそれが必要なタスクであるかがわからないことが課題です。タスクによって必要な成果物がすべて網羅されていること、そしてその成果物ができるのがプロジェクトのタイムラインに対して妥当な時期であるかをクライアントと共に確認し、合意することが重要です。
③ 必要コストの見極め
コンサルティングプロジェクトにおけるコスト管理は、実はあまり複雑ではありません。コストのほぼすべてがコンサルタントの人件費だからです。そのほかにはインタビューコスト、資料の購入コスト、交通宿泊費なども発生しますが、太宗を占めるのはやはり人件費でしょう。
とはいえ人件費が大半だからといって、コスト管理がいらないわけではもちろんありません。スケジュール設計の際に、必要工数を見積もるのは当然ですが、不確定要素に備えたバッファとしての工数をどこまで積むべきか?という点について見極めなければなりません。バッファを積みすぎるとクライアントに課題に請求することにもなりますし、少なすぎるとトラブル発生時の対応可能性が下がってしまいます。そのため、適正なコストを見極めるたえには、不確定要素を潰す必要があります。そして不確定要素を少しでも減らすためには、スコープやスケジュール設定時のアウトプットの合意をクライアントと合意しておくことが求められます。
④ 会議体とコミュニケーション方法の設計
プロジェクトはコンサルタントとクライアントが二人三脚となり検討することで進んでいきます。プロジェクトによって多少スタイルは違うかもしれませんが、調査・分析→報告・討議→意思決定のサイクルを回しながらインクリメンタルに進めていくことが一般的でしょう。コンサルタントは、このサイクルを回していくための会議体を設計する必要があります。例えば課題の内容によっては、カウンターであるクライアント部門以外の様々な部署の協力が必要であったり、マネジメント層の意思決定が必要なものであったりと、プロジェクトチーム外の参加者が多岐にわたることがあります。課題検討・解決・進捗のために必要なメンバーと必要なプロセスを理解し、そのうえで最も効果的・効率的な会議体やコミュニケーションプランを設計することが重要です。
終わりに
本稿では、プロジェクト計画の基礎として、PMBOKにおけるプロジェクト計画の要素を参照しながら、コンサルタントとして特に重視すべきポイントについて解説しました。プロジェクト計画の良しあしは、プロジェクトの成果に直結するといっても過言ではありません。
コンサルティングにおけるプロジェクト計画は、実際は提案時に策定するのが一般的です。提案時にすべてのプロジェクト情報が揃っていることはほぼなく、ある種暗中模索で策定せざるを得ないことが多いのですが、クライアントとの提案前討議において、解くべき課題を設定し、あるべきプロジェクト計画を策定します。すなわち、クライアントの課題解決のためにどうあるべきかを真剣に考えることなしに適切なプロジェクト計画は策定できないでしょう。ファームによっては、プロジェクト計画はもとより、課題に対する答えの半分程度を提案時に提示するところもあります。コンサルタントはプロジェクト計画を単なる作業計画としてではなく、課題解決のために適切なものとして策定することが求められていると意識しなければなりません。

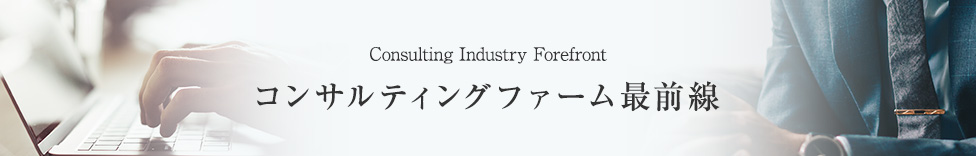



 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in