はじめに

コンサルタントにとって、ネットワーキングは仕事を活性化し、成功へとつなげる不可欠なスキルです。ただし、そのネットワークは自身の選好ではなく、目的をもって積極的に構築することが重要です。
本稿では、コンサルタントにとってのネットワーキング戦略について、内部向けのネットワークと外部向けのネットワークの二方面から述べていきます。
特に昨今のコンサルティング業界においては、ネットワーキングは、これまで以上に重要な価値を持つようになってきています。その理由と検討すべき方向性について述べていきたいと思います。
内部向けネットワークの重要性
内部向けネットワークとは、所属するファーム内で構築される人間関係や情報共有の仕組みを指します。コンサルタントにとって、組織内でのネットワークを効果的に活用することは、プロジェクトの成功に直結します。
特に考慮すべきなのは、コンサルティングファームの縦割り化と、クライアントの取り組むテーマの業際の拡大という相反する流れをどうマネージするか、という観点です。
コンサルティングファームの内部組織の縦割り化の弊害
2024年現在、国内のコンサルティングファームは総体としては成長の方向性にあります。コンサルティングファームの成長は依然として従事する人員数によるため、コンサルティングファームの成長は即ち人員数の増を意味しています。
人員数が大きくなると、当然各組織の規模は大きくなり、その組織内でたいていのプロジェクトは完結するようになります。それ自体は当然問題にはなりませんが、考慮すべきは組織間の人材の流動性が下がることです。
組織が拡大すれば当然組織のKPIも高い目標となり、それを達成するためには多くの場合組織内でのプロジェクト運用が重視され、各組織は内向きにならざるを得ません。プロジェクトにおける組織間の連携は薄れ、インダストリーやプラクティス間のナレッジは共有されなくなってしまいます。
クライアント課題の業際の拡大
一方で、クライアントの解くべき課題の範囲は拡大しています。例えば自動車業界はEV化の流れにおいて、充電問題の解消や逆にEVを活用した宅内向けエネルギーマネジメントサービス、電力の需給調整に対するサービスを検討しています。
すなわち、自動車業界と電力業界の課題を同時に検討する必要があります。
こうしたクライアントの課題の範囲の拡大に合わせ、コンサルティングファーム側も本来はクロス・インダストリーの体制をとるべきですが、前述のような縦割り組織の弊害が、そうした体制構築のハードルになることがあります。
内部ネットワーキングの重要性
そのため、現在改めて重要になっているのが内部ネットワーキングです。ここでの内部は自組織内というよりも、自社組織間のネットワーキングを意味しています。
クライアントの業際の拡大に合わせ、考慮すべき他業界における課題をいかにファーム内で共有し、それらを踏まえた提案やデリバリー体制の構築ができるかが、コンサルティングファームに求められる新たな価値と考えられます。
ファーム内で組織単位の壁があるならば、組織ではなく人単位でのネットワークを構築し、クライアント課題に対面していくことが、個々人のコンサルタントに求められることではないでしょうか。クライアントでは容易に超えられない業界間の壁を越えた提案ができてこそ、コンサルティングの価値が生まれるはずです。
外部向けネットワークの重要性
外部向けネットワークは、更に2つの領域に分かれます。1つは専門的な知見を得るためのエキスパート・ネットワーキング、そしてもう1つはリクルートのためのネットワーキングです。
独自のエキスパート・ネットワーキングの構築
専門的な知見を得るためのエキスパート・ネットワークは、従来はコンサルティングファームの専売特許でした。クライアントでは得難い情報を独自のネットワークを用いて収集・整理し、クライアントにとっての意味合いを提示することは、クライアントがコンサルタントを登用する価値の一つでした。ところが、最近GLGやビザスクのようなエキスパートインタビューサービスが一般化しつつあり、事業会社でも容易にアクセスできるようになっています。そうなると、わざわざコンサルタントを介さなくても・・・という会社もでてくるようになってきました。
もちろん情報収集のためのフレームワークやテクニックは依然としてコンサルティングファームに一日の長があると考えていますが、とはいえ情報ソースへのアクセスという観点では付加価値が減少しているのは事実です。今後のコンサルティングファームに求められる外部ネットワークは、そうしたエキスパートインタビューサービスにはないような、独自の情報網と、より深いつながりです。
そのためには、ファームに属するコンサルタント自身が自らの専門領域や業界に関する情報を積極的に発信し、それを梃(てこ)にして社外との交流を深める必要があります。こうした取り組みを通じて、従来の枠組みを超えた知見や協業の機会を得ることができ、結果としてファームにおけるサービスのさらなる差別化につながるでしょう。
これからの時代、クライアント企業が直面する課題は多様化・複雑化しています。そのため、ファームの外に向けた新たな活動を継続的に行い、より幅広い情報ソースや洞察を獲得することが不可欠です。
リクルートのためのネットワークの構築
先ほど、国内のコンサルティングファームは総体としては成長の方向性にあると述べました。また、コンサルティングファームの成長は人員規模の拡大によってなされるとも申し上げました。それが意味するのは、市場は今、有望な人材の取合いの状況にあるということです。
ただし、一時期は(失礼な言い方になりますが)それこそゲタを履かせてでも、ポテンシャルという名のあやふやな期待値で大量に人を採用する状況でありましたが、さすがにそこまでの過熱した状況は落ち着きつつあります。大手各社があまりにも大量採用をしすぎたため、採用した人材の教育すらままならず、コンサルタントとも呼べないような人たちが参画することによるトラブルプロジェクトが多発したからです。
その代わり、有望な人材や既に他社で実績のある人材の取り合いになっています。そうなると、重要になってくるのがリクルートのためのネットワークの構築です。
エージェントを介した転職活動が一般的ではありますが、エージェントもビジネスで転職を仲介しているため、必ずしもその人にとって最適なファームではなくても、少しでも可能性があれば紹介をしてきますし、(彼らにとって見返りが大きいため)少しでも給与の高いファームに転職希望者を紹介する傾向があります。そのため、お互いにとってミスマッチが起きることも少なくありません。
例えば著者は複数のコンサルティングファームを経験していますが、これまで在籍してきたファームのつながりを活用するのは最も一般的な手段です。シニアやジュニア問わず、今のファームに必要な人材がいないか、あるいは転職を考えている人材を紹介してもらうために定期的にコミュニケーションをとるようにしています。
最終的に人材を判断するうえで最も頼りになるのは一緒に働いたことのある同僚の意見です。そのために必要なネットワークを構築することも、(特にシニアクラスの)コンサルタントにとって重要な活動です。
終わりに
コンサルタントにとって、ネットワーキングは単なる手段ではなく、成功に直結する重要な戦略です。内部ネットワークを活用して組織内のリソースを最大限に引き出し、外部ネットワークを通じて新たな機会や知見を得ることが、クライアントに対する価値提供を可能にします。これらのネットワークを効果的に構築・活用するためには、日々の努力と戦略的なアプローチが欠かせません。
ネットワーキングは一朝一夕で築けるものではありませんが、長期的な視点で取り組むことで、コンサルタントとしての成長と成功を確実なものとするでしょう。本稿が、読者の皆様がより効果的なネットワーキング戦略を構築するための一助となれば幸いです。

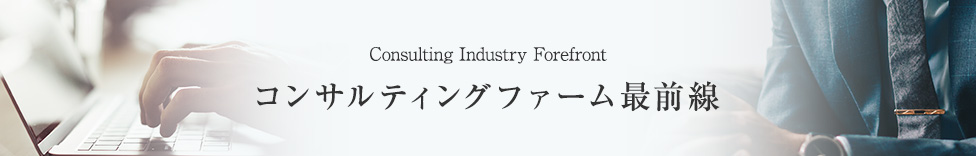



 Facebook
Facebook
 Linked in
Linked in